中国人との交流と中華料理
中国に約10年も暮らしているあいだ、住居地は皆大都市ばかりである。中国は近代化がすすみ経済的に発展しているが人口比でみると依然農業国といってもいいだろう。
大連郊外のとある農村で北方地帯の特色あるレストランへ出かける機会があった。
■中国人と近郊農村の田舎料理店へ

大連交通大学で中国語を学んでいる「国際文化交流学院」には日本人が主催している囲碁クラブがある。私は学生時代以来、数十年間途絶えていた囲碁に興味をもち、クラブに参加した。
クラブの会長「三浦」さんは、戦前に旅順の大学を卒業して以来、今日まで日中の貿易商を営み、大連市で中国人との幅ひろい交流がある方である。その縁で囲碁クラブに隋さんや李さんが参加している。
あるとき、歓談中に隋さんが、
――大連郊外の農村に田舎料理を食わせる店があるので、一緒にいこう。
と誘ってくれ、フォルクスワーゲンを運転する李さんに同乗して、5人で出かけることになった。
■大連市金州地区向応鎮土門子村
大連市を北上し、金州区をとおり北に向かうこと1時間で、「呉家小院」という農家についた。
まずは、待合室でお茶がふるまわれた。
入口に大きな竈があり、鍋にはサツマイモがこんがりと焼きあがっている。家の前にも大きな鍋があり、ふかしたての包子があった。餡は野菜でとてもヘルシーだ。芋と包子を一つずつ食べた。とても美味しいので更に食べたいほどだが、楽しみの昼食が食べられなくなるので我慢する。
■農家料理

大皿に盛られた各種料理に「取り箸」はなく、自分の箸で直接取る。この中国式食事マナーは、団体旅行で見知らぬ他人と一緒に食事するときも同様である。
とりたてて変わったものがあるわけではないが、素朴な味に舌鼓を打つ。それにしても中年以上の5人には、このボリュームいっぱいの料理は食べきれない。最後にでた焼き芋と包子といっしょに残りは打包(持ち帰り用のパック詰め)にしてもらった。なお、大連など北方系の典型的な小麦文化圏の料理では米飯が出ないのが特色らしいが、料理名は女性の辻本さんが解説してくれた。
食事中に李さんがお尻を床から浮かすヘンな仕草をしているのが不思議だった。そのうちに私のお尻がポカポカと暖かくなってきたので理由がわかった。ここは北方系の農家特有のオンドル暖房だったのだ。
中国では畳が廃れて以来、椅子に腰掛けるのが一般的だが、ここでは、オンドルの上に座ったり、布団を敷いて寝ている。5月になっている今でも、北方では朝晩冷えるのでオンドル暖房をしているが、本日の昼時には太陽が照っていて暖かいので、かえって暑いくらいだ。隣室が炊事場で竈の排熱がオンドルに伝わって各部屋を暖めている。
昼時には、他の多くのグループの客も食事していた。

快い微風のなかで囲碁の熱戦
さて、我々囲碁クラブの仲間は、食後に囲碁を楽しむのが他の客と違う。隋さんなじみの老板(店主)は、我々が囲碁をはじめようとすると、さっそく椅子と机の用意、さらにテントまで張ってくれる用意周到さであった。
五月の昼下がり、日陰で微風が頬をなでる心地よい気分の中で囲碁を打つことができるなんて、何と贅沢な遊び方だろうか(碁盤と石はクラブから持参)。
夕日が西に傾きかけた頃、大連への帰り道に「帰田居」と呼ばれる古風な住居に立ち寄った。
その名前は、漢詩に覚えがある人なら、 東晋時代の園詩人陶淵明を思い出すであろう。代表作「帰去来の辞」の最初の2句、歸去來兮 田園將蕪胡不歸
(帰りなんいざ 田園まさにあれなんとす なんぞ帰らざる)
は特に有名である。
陶淵明には、上の詩の姉妹作「帰園田居」もあるので、「帰田居」は、この詩から発想して命名したのか。

じつは、このときより、5、6年前に陶淵明の故郷九江市郊外の「陶淵明記念館」を訪れたことがある。だが、「記念館」の周囲は殺風景で陶淵明が晩年過ごしたといわれる田園風景の面影はまったく見られなかった。
しかし、大連郊外の緑豊かなこの地にひっそりと佇む帰田居は陶淵明がすごした地を彷彿させてくれる。
この建物は財を成した不動産業者が建てたそうだが、たんなる金儲け主義の業者ではなくて、陶淵明に思いをよせる風流人なのだろう。現在「帰田居」は食堂兼宿泊施設に転用されており、食事用個室や寝室は中国風オールドファッションなので、日本の友人がきたら案内すれば喜ばれるだろう、と隋さんがいっている。
こうして一日、囲碁仲間と大連の農村地帯を訪ねて田舎料理を堪能できたし、隋さん、李さんのような中国人と親しく交流する機会を得たことにも満足した。そして隋さんが、日本人が興味を抱きそうなスポットを案内してくれたのがうれしい。
■中国人の家庭訪問
私は、大学の教師だったので、学生など中国の若者とは日常的に交流してきたが、彼らの親の世代などの大人と交流する機会は意外に少ない。
外国人で単身赴任者の私は、中国人の家庭やその両親を知り、そこで人間的な営みを垣間見ることができれば、と念願しているのだが・・・。
それがわずかながらも、実現できた例を以下に紹介しよう
●その一
昆明の大学の班長であり、地元出身の「莫」君とは特に親しくなり、家内が昆明を訪問したときには、彼の父の車で市内の案内までしてくれた。春節の大晦日(日本での12/31に相当)、集合住宅の門前で、爆竹の炸裂音で私を驚かせる演出で迎えてくれた。莫家にはいると、祖父母、父、そして、おそらく珍客(?)日本人への興味か、二人の叔母まで同席して、歓迎してくれた。
おじいさんは、共産軍の元軍医だったそうだから、莫家は庶民よりは、社会的地位がたかいのだろう。

机上の晩餐の盛り皿に、取り箸がついていた。莫君か彼の父が日本のテーブルマナーを知っているのだろうか? 私はそんな行き届いた気配りがうれしかった。

●その二
奇岩が山頂まで林立する有名な観光地湖南省の「武陵源」を訪れたとき、同行した学生の一人「覃」君のお宅の夕食に招かれた。小柄な祖母を中心に家族と我々が取り巻くように食卓についた。「その一」と同様に、三代の家族が住む中心に祖父母がいる、長幼の序や敬老の美風が地方へ行くほど残っているのが微笑ましく思えた。
●その三

無錫の大学に赴任したとき、若い教師「蒋」先生がバスで1、2時間の彼の故郷「宜興市」の鍾乳洞に案内してくれた。
そのついでにご家庭に案内された。彼の父は大学の教授だから、庶民よりは裕福な家庭なのだろう。背後の窓に注目されたい。このお宅は、集合住宅の2、3階にあったが、窓は、堅牢な格子で守られている。これは、中国では必須の盗難防止の鉄柵である。
■中華料理

A 水餃子
水餃子は中国ではポピュラーで、長安大学時代には学生が我が宿舎に来てよく作ってくれた。私が日本で好物の焼き餃子は中国では稀らしくて、聞くところによると、水餃子の残り物を翌日焼いてたべる程度らしい。
B 火鍋
これは四川料理から全国に広がった。街中の火鍋は安いので、多くの学生に奢ってあげても私の給料で困らない。体を温める冬の味覚として最高である。隔壁で二種類のスープを楽しめる鍋を「鴛鴦(おしどり)鍋」と優雅な名前がついている(写真下中央)。写真右の「炊鍋」は雲南省昆明で見たもの。火鍋の一種であるが、かつて電力が無かった時代に、煙突の中に炭火を熾らせて炊いた名残らしい。

C 雲南省料理の「米線」と「タイ族の庶民料理」
米線は熱々のスープに具と米麺をいれる雲南特有の食品である。過橋米線は直訳的英語で「Cross Bridge Rice Noodles」と書く。その麗しい由来はインターネットでご覧あれ。
タイ族料理は、中国の最南端雲南省の更に最南端の「西双版納傣族(シーサンパンナタイ族)自治区」に旅行していたときに、庶民のレストランで食べた。料理は素朴な味でよかったが、タイ族の民族の名前が、漢字で「傣族」と書く点にも興味をひいた。傣族は、タイ国に住む泰(タイ)族と民族的に近いそうだが、中国政府は両者の名称を区別している。

D『客家』家庭料理
客家はもともと中原に住んでいた漢民族の一部が戦乱や異民族の支配から逃れて、南方に移住してきた人々である。そこでは、先住者から“よそ者(招かれざる客)”として『客家(はっか)』と呼ばれ、相互の軋轢が発生した。そこで、外敵から身を守るために、厳重に防御されている土楼を建てたり(福建土楼が有名)して、独立心旺盛な自立生活をしている。
わたしが、江西師範大学で教鞭をとっていたとき、江西省南部の山岳地帯とその隣接地方出身の教え子のなかに客家が何人もいた。「仏教寺院巡礼の旅」で同伴してくれた黄さんも客家の子孫であることはすでに触れた。
作文授業で或る学生が、「客家の我が家では独特の郷土料理を作っています」と書いていた。客家は居住や農業に悪条件の山間部やその周辺にしか定住できなかったので、その過酷な環境に順応した食文化が育まれたようだ。

酿豆腐:豆腐に割れ目を入れて肉の餡を挿入して煮る(or焼く)。
酿辣椒:唐辛子にスパイスのきいた魚や肉を詰めて焼く。(酿niang=釀)
作文の添削で「食べてみたい」と感想をそえると、お母さんが作った料理をわざわざ我が宿舎へ運んでくれた。上の写真の二つが典型的な客家料理で、やや塩分の濃い味がした。こうして、特異な漢民族集団「客家」に食品を通じてふれることができたのは貴重な体験である。
なお、客家は海外(華僑)も含めた総人口が1億2千万人というから、日本の人口に匹敵する大勢力である。歴史上、思想家、革命家、政治家など有能な人材を輩出している。
朱熹(朱子学の開祖)、文天祥(南宋末愛国者)、洪秀全 (太平天国の乱)、孫文(辛亥革命指導者)、鄧小平(改革開放の政治家)、李登輝、蔡英文(共に台湾総統)、リー・クァンユー(李光耀、シンガポール初代首相)など。

E 小籠包
日本語教師として家内と中国にはじめてきたとき、上海の名所「豫園(よえん)」へ行き、「南翔饅頭店」で小籠包を食べた。湯気が立ち昇る深みのある白いモノを一口食べたとたん、家内が感動の声を発した。
「まあ、おいしい!」
私もうなずいた。
だが、箸の扱い方がぞんざいなのか皮が破れてスープがこぼれでたり、熱くて舌が火傷しそうだった。隣のテーブルの客が箸とレンゲで口へと運んでいる。それがこの繊細なモノの食べ方らしい。
最初に赴任した西安市では、湯包(タンバオ)と呼ばれている。一つ5元の蒸篭を二つと、5元の瓶ビールを注文すると、合計15元(ほぼ20年まえの元円レートで200円)で、絶品の夕食を腹いっぱい堪能できた。
こうして小籠包を食べているうちに、私はこの佳き食品のいっぱしの《通》になった気分でいる。美少女の柔肌に触れるように優しく箸で摘まみ上げ、小皿のタレに浸けてから口にふくむ。熱くても舌で転がしながら、空気を吸いこめば、頃合いの温度になって火傷をすることもない。レンゲを使うなど野暮天のやることだ! 台湾系の店では千切りの生姜が添えてあり、ちょっとピリッとした乙な味も悪くない。牛肉や羊肉と較べて、野菜入りもヘルシーでいい。
西安に二年間住んだあと、私は無錫の大学に赴任した。この地の小籠包の店に着任早々出向き試食した。とても甘くて、お菓子(点心・甜食)を食べているようで、夕食にはならないと失望した。
その五年後に今度は上海の大学に赴任した。
市内のチェーン店では豫園とさほど劣らない味で、安い小籠包を食べることができるし、無錫ほどには甘くないので満足した。
こうして上海の小籠包の味に舌が慣れた一年後に、懐かしい西安に旅行した。回族が多く住む「北院門街」で久しぶりに小籠包を食べたら、塩分の濃い味がした。
北国西安の塩味と南国江南地方の甘味との地域差は、中国の気候風土の違い、ひいては文化の多様性を物語っているのだろう。だが、それぞれに特色ある味で結構だ。絶品小籠包こそ中国料理の中の王様、いや皇帝である。
F 羊肉串
羊肉串を紹介する前に、家庭訪問「その三」で窓に鉄格子がはめられていた話題のつづきから始めたい。
江西師範大学では、十数階のマンションの十階に教師用宿舎があてがわれていた。これほどの高い位置にある窓には防犯用鉄格子は無く、私は窓外の山々の眺望を楽しんだ。
しかし、あるとき泥棒ではなく、ネズミが二匹宿舎に出没したのにはびっくり仰天だ!
――壁や雨樋を伝ってこんな高いところまで登ってくる?
さっそく学生にネズミ捕り籠を買ってきてもらい、首尾よくとらえることができた。不要になった籠を捨てようとしたら、ある学生が「私にください」という。
「故郷のおじいちゃんが、ネズミを捕って食べるのです」
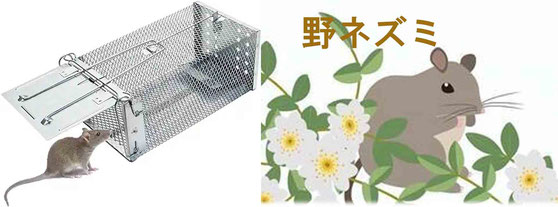
大都会の薄汚れたドブネズミなら不衛生だが、山野に棲み草花や穀類を食べている健康な野ネズミなら、中国農村の老人が好む風習は納得できる。小籠包でも、野菜入りは健康によいではないか。
あるとき授業で「日中の食肉文化の差」を紹介した。
――統計によれば、中国の猪肉(豚肉のこと)に対して、日本では鶏肉の消費量が一番多い。私は、サラリーマン時代には、“焼き鳥”が大好きだったが、中国に来てからは、代わりに“羊肉串”をよく食べています。
授業の後で一人の学生がこっそりこんな話をした。

「先生、路上の屋台で売っている羊肉串には、ヘンな肉が混じっているかもれませんよ。ちゃんとしたレストランで食べてくださいね」

ついでながら、私が教師宿舎で学生に振舞い、人気があった日本食品は左のようなものであった。(大連市だけは、食材すべて現地調達できた)
