3 江鈴杯スピーチコンテスト
●師範大学日本語科の学生が参加するスピーチコンテストの一つは、江西省の大学・専門学校の学生が競う『江鈴杯』スピーチコンテストである。
ここから、私にとって思い出深い2009年の大会の模様を紹介したい。
この年のテーマは『氷河を乗り越えよう』であった。前年が『桜と私』で、“フジヤマとゲイシャガール”に似た日本への大時代的ステレオタイプの憧れをイメージさせるテーマであったのに対し、この年は経済状況の厳しさを反映したテーマとなった。前年秋にアメリカで発生したリーマン・ショックが引き金となり、世界同時不況の波が中国にも押し寄せ、日本語科の卒業生の就職難が深刻となっていたのである。日本の新聞にも、しばしば学生の就職難を『氷河期』と形容して報じていることより、このテーマの意味するところは明かである。
まず日本語科の予選大会で4名が代表に選ばれた。つぎに、『テーマ』にふさわしい内容を作文にして大会運営事務局に提出し、書類選考後2名が大会に出場できることになっている。日本語科の予選を通過した学生は、2、3年生それぞれ2名であった。何れも女性で、女学生が圧倒的に多い女性上位の日本語科では、ひ弱な男子学生が割り込む余地が少ないのだ。
『氷河を乗り越えよう』はタイムリーなテーマではあるが、海外からいきなり飛んできた火の粉から如何に身をかわして対処していくべきかが問われている難解なテーマといえるだろう。特に卒業が2年先で切実感に乏しい上に、十分な作文の訓練を受けていない2年生はとても苦労したようだ。
早々に秀作を書いてきたのは3年生の鐘文濤だった。要約するとこうなる。
――大学院進学を夢見ていたが、父が会社の倒産で職を失ったことを知って、進学を諦めた。しかし父は、必ず再就職するから家のことを心配しないで大学院進学の夢を持ち続けよ、と母と共に激励してくれた。父母との絆の深きことを再認識し、大学でバイトをしながら進学の意欲に燃えたのだった。
このように彼女の作文は、『経済の氷河期』『家庭の氷河期』『自分の氷河期』と巧みな筆の運びで説得力あるスピーチにまとめ上げている。本大会で上位入賞を狙える、と私は手応えを感じた。
数度書き換えた二年生の陳も、ようやく作文を完成させた。
――憧れていた華やかな大都会への就職を断念し、緑ゆたかな地方都市の故郷に帰り、地道に働いて田園の中で人間らしく生きてゆくことにしたい。
と書いていた。帰りなんいざ!(帰去来の辞)と故郷へ回帰した陶淵明の現代版みたいなものだった。
三年生の李はクラスでも一、二を争う優秀な学生で、作文でも深みのある内容を書いていることが多かったので一番期待していた。しかし、テーマが自分に合わなかったのだろうか、今回は平凡な作にとどまった。
こうして、三人の作文は完成したが、二年生の劉嘉瑢の作文には、私は悩まされどうしであった。
初稿では「『人間万事塞翁が馬』だから、苦難の中にあっても悲観するな」と、諭した祖父の助言の部分だけはよかったが、他はハシにも棒にもかからない駄文だった。その故事をフィナーレで有効に使うことにして、他の部分の全面的書き直しを命じた。が、三度目に書いてきた文章を読んでいて、私は呆れかえってしまった。書き直しの苦労話を縷々書き連ねた挙げ句に、
――何度も書き直しを命ずる教師の厳しい要求に耐え抜くことが、私の『氷河を乗り越える』ことだ。
と、ぬけぬけと書いていた。
お前はバカか、そんなもの苦労でもなんでもない! いまスピーチ草稿を練り上げている各学校の学生たちは、『氷河』という経済不況にどう立ち向かうべきかについて、悪戦苦闘しながら完成を目指しているというのに。しょせん、2年生の作文とはこんなものか、と私は匙を投げ出した。表現上の文言だけ訂正して、これでOKとした。どうせ書類審査で落とされるだろう、と私は思った。
4人の作文を提出後、一週間して書類選考による合格者が知らされた。鐘が合格したのは当然として、もう一人が劉だったのには驚いた。私は本テーマの意図するもの、そして審査委員の評価基準が分からなくなってきた。こうして、鐘と劉の二人が本大会に臨むことになった。
その一週間後、江鈴杯スピーチコンテストが、師範大学旧キャンパスの学生会館で開催された。私が住んでいる郊外の新キャンパスと比べて旧キャンパスは、賑やかな街の中にあり、学内もごみごみと立て込んでいた。
私が到着したころには、先に集まっていた出場者21人が出場順番のクジ引きをしていたようである。
鐘は、いの一番に出場という、貧乏クジを引いてしまった。
学院長、来賓などの挨拶の後、コンテストがはじまった。
第一番の発表者鐘が演壇に向かった。
演壇に立ってスピーチを始めた彼女を見て、これはまずい!――と私は思った。
演壇が高すぎるので、小柄な彼女は肩から上が見えるだけであった。

私はフロアの前寄りの座席にいたが、最前列に座っている審査委員から見たら、鐘は首から上しか見えないだろう。これでは時代劇に出てくる罪人のさらし首のようだ。演壇上に置かれた鐘のさらし首が、パクパクと口を動かしているかのような光景は、見た目の印象がすこぶる悪いではないか! 彼女の足許に20センチほどの踏み台を置いて欲しかったが、今更大会運営者に苦情を言っても手遅れだ。
しかし、鐘は落ち着いており、よどみなく話し終えた。彼女は元々地味な性格であり、淡々と話す口調からは審査委員に強い印象を与えるほどではなかったかもしれない。
司会者が5人目毎に審査委員の評価点を発表することになっている。5人目が終わった時点での私独自の評価では鐘が最高点であったが、司会の発表によると、既に鐘を上回る得点者がいて、今のところ鐘は第二位であった。しかし、各発表を聞いているうちに、私はとても違和感を覚えはじめた。
△それは、『氷河を乗り越えよう』というテーマが経済危機やそれに伴う就職難への対処法とは違って、人生における危機や困難を乗り越えることに拡大解釈した発表ばかりであったからだ。たとえば、不幸な戦争の苦難を乗り越えて中日友好の未来を謳い上げている者、四川地震に真っ先に駆けつけた日本の救援隊への感謝と痛手からの復興を訴えた者、学校でイジメにあった苦悩を克服しようとする心の葛藤を述べた者、一級試験合格後の倦怠とそれからの脱却を述べた者、などである。
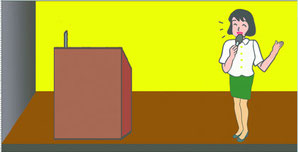
△ある女学生の発表には呆れた。彼女は舞台にあがってから、演台からマイクをとり、ステージ中央前寄りに立ってまるでカラオケで歌を歌うようにスピーチをはじめた。清楚なブラウスと短めのスカートの下に脚線美を誇示し、表情豊かに審査委員に直接語りかけるブリッ子のような態度が、私には鼻についた。おそらく、小柄なその女学生は演壇の後ろに立ったら、鐘のように首から上しか見えないので、不利だと考えたのだろう。それは、彼女を指導している教師の入れ知恵に違いない。しかし、一人だけ演台を離れてスピーチするのはアンフェアーである。なぜ、こんなことを審査委員は許しているのだろうか、と私は不快でならなかった。
10人の発表が終わったところで、鐘の順位は既に4番目に落ちており、上位入賞は夢と消えた。
私はそこで席を立ち、会場の外へでた。応援にきている各校の学生たちが会場の建物の周辺にたむろしている。5月の太陽が強く差し込んでいて汗ばむほどの陽気だった。私は構内を散歩して、とある木陰のベンチに腰掛けた。
発表者たちのスピーチを反芻してみた。私は、テーマ『氷河』を経済危機あるいは不況による就職難と限定的に解釈したことが、正しかったのかどうかを考えた。少なくとも、他校の学生のスピーチでは、『氷河』をかなり拡大解釈して、天変地異でもいいし、個人的・家庭的な環境など全ての好ましくない激変と理解していたことが明らかである。
中国には『上有政策、下有対策』(上に政策あれば下に対策あり)という諺がある。
中央政府が打ち出した政策が地方の利益にかなわぬとなれば独自の対策を講じて、中央政府の政策を骨抜きにする――という、中国四千年の歴史から生み出された知恵であり、現代中国でも有効に活用されている手段であるらしい。
してみると、江西省の各大学日本語科の諸先生が、『氷河を乗り越えよう』を『上有政策、下有対策』で見事に骨抜きにして、融通無碍な発想でこの大会に学生を送り込んできたのだ。
一方、昨今の経済情勢の中では『氷河』とは経済危機によって発生した諸困難に限定された意味であるとしか受け止めなかった私は了見が狭かったのだ。「一本参った」と、自分の額を掌でピシャリとたたいた。
スピーチコンテストで、我が校は日本人教師がほとんど総てを取り仕切っている。学内の予選大会の運営からはじまり、発表草稿の作文指導、発音や発表態度の指導、そして、コンテスト会場まで常に学生と行動を共にする。
一方、中国人教師は総じて課外活動には関心が薄い。大学によってはコンテスト会場に一人の中国人教師も応援にこないこともあった。そんなことは、日本人教師に任せておいたらいいことで、家庭を持っている教師が休日を犠牲にしてまですることではない、と、ビジネスライクに考えているのだろう。一方、日本人教師はビジネスライクに割り切れないという意味で、アマチュア的だ。
アマチュアだからやり過ぎることもある。無錫市には『太湖杯スピーチコンテスト』があった。私は無錫の短大で、大会に出場するために、まず、6、7人の学内予選出場者を指導し、次に代表に選ばれた2人にはいっそうの指導をした。大会直前には、私と学生との宿舎が同じキャンパス内の近くにあったので、私の宿舎で猛特訓は夜遅くまで続いた。ようやく終わった頃には11時近くになっていただろうか。私と女学生はベランダに出て、快い夜風にあたりながら満天の星を眺めていた。教師が学生と同じ目的に向かって、心を一つにしていることの充実感を味わっていた。向かいの建物は中国人教師の宿舎になっているらしい。そこに、黒い影が見え隠れしていた。私は、ある予感があって、すぐ学生と室内に戻った。後日、私の予感が当たっていたことを知らされた。
――森野老師は、夜なよな可愛い女学生を宿舎に連れ込んで、よろしくやっているらしいぞ!
中国でも日本と同様に、口さがない雀のさえずりや、やっかみ半分のカササギのうわさ話は避けられないもののようだ。私は、言わせておけ、とばかり、無視することにした。
そんなことを思いだしながらタバコをふかしていると、劉がぶらりぶらりと歩いてくるのが見えた。発表順番は、鐘が真っ先だったのに、劉は最後である。待ちきれなくて散歩でもしているのだろう。彼女が私に気付き近寄ってきた。
「ここに座りなさい」と私は劉を促した。「わたし、今回のテーマを読み違いしていたようだ。案外劉さんの発表はいけるかもしれないよ。先生、そう思えてきたんだよ」
「本当ですか。でも、作文を書いていたときには、一度も先生から褒められたことがありません」
と、劉は半信半疑のようだ。
「それは申し訳なかった。けど、皆の発表を聴いていて、そう思うようになったんだよ」
「嬉しい! じゃ先生、もう一度ここで発表の練習をしますから、聴いてくださいますか」
劉はこういって、私の前2メートルに立ち、最後のリハーサルをやった。
劉は丸顔で、笑うとエクボが可愛いが、それでいて、けっこう図太い神経をしている。発表草稿の作成中も、私が何度書き換えを命じてもある一点では譲らない頑固な面もあった。
会場に戻った。最後部座席の後ろで立ち見している学生の多くが、師範大の学生だった。皆の関心は劉の発表に集中していた。

●そして、いよいよ劉が最後の発表者として登壇した。コンテストがはじまって既に3時間半が経過しており、会場には“聴き疲れ”による倦怠感が漂っていた。最初に発表した鐘が不利であったのと同様に、最後の劉にとっても有利な順番とはいえないだろう。
しかし、劉は、落ち着いた口調でスタートし、メリハリのある話しぶりで語り続けた。話の趣旨は以下のようなものであった。
――スピーチコンテストの草稿づくりが大変なことをはじめて知った。指導教師の酷評に耐えながら改作を繰り返しての毎日は地獄であった。最終稿を完成させた時に、ふと祖父の言葉を思いだした。祖父は文化大革命時代に教師をはじめた。先輩教師が紅衛兵につるし上げられた苦難の日々の中で、『人間万事塞翁が馬』を信じて堪えていたそうだ。人は幸福に見えたときに不幸の落とし穴に嵌っているかもしれないし、一方、不幸と思える最中に幸せの芽が育ち始めていることだってあるのだよ、と祖父が諭してくれたのだ。わたしは今回、ささやかながら試練をひとつ乗り越えてきた。この貴重な体験を糧として、将来の厳しい実社会に立ち向かう心構えとしたい。
△劉はこう結んで、制限時間以内にスピーチをまとめ上げた。
私は当初、彼女が、テーマ『氷河を乗り越える』の主旨をスピーチ草稿作成時の苦労話に矮小化させたことに大いに不満だったが、本大会中の他の発表者が“人生の苦難”一般へと拡大解釈してスピーチをしている中で考えると、劉の発表には何ら違和感を覚えなかったし、むしろ堂々たる発表態度に満足すらした。この後に審査委員との質疑応答に移った。劉はここでも、的確に答えたし、ユーモア溢れる話しぶりにフロアから笑い声を誘った。応答態度も評価点に反映されるので、これはいい、と私は思った。
昼食の休憩をはさんで、午後から結果の発表と表彰式があった。
劉は準優勝だった。まだ2年生の彼女としては上出来だ。入賞者たちが並ぶステージの中央で、審査委員長から表彰状と副賞を受け取って、満面の笑みを浮かべていた。鐘は21人中10位でやはり賞状を受けた。このようにして、師範大が本年も大健闘した。
しかし、私は喜んでばかりいられない。本大会のテーマを読み違えてしまって、劉を過小評価した反省がある。今回も発表草稿の指導方法の難しさを感じさせられたコンテストであった。
